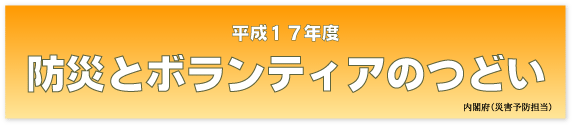 |
| 分科会C 「地域のたすけあいと防災ボランティア活動」 コーディネーター 馬場 正一 氏(兵庫県社会福祉協議会地域福祉部長) 【関連する資料はこちらから】 分科会の趣旨説明と自己紹介 馬場氏(兵庫県社会福祉協議会地域福祉部長) この分科会のテーマは地域の助け合いと防災ボランティア。東京のほうも雪が降って、これも一つの災害ではないかと思うが、災害は非日常の事態であり、行政機能を含めた社会的な機能のほとんどが麻痺するという事態が大規模災害である。ただ、発災直後は、近隣住民、地域の中で救助や安否確認などが行われる。そういうことを念頭に置きながら、ふだんからの地域づくりや助け合いの仕組みづくりと、防災のボランティア活動との連動を考えていくことがこの分科会の趣旨である。 話題提供 【社会福祉協議会の取り組み紹介】 ・地域に住んでいる障害者の方の名簿を民生委員さんにお配りして、民生委員さんが自分の担当地域に障害者がいるのかを把握している。 【NPO団体の取り組み紹介】 ・パネル展示コーナーでも紹介しているが、一昨年、新潟県川口町での災害支援のボランティア活動を紹介している。活動はボランティアセンターが立ち上がったばかりの時期で、必要なニーズとそうではないニーズがあり、それはどんどん変わっていった。 グループワーク1の概要と発表 Aグループ ・Aグループでは、五つのキーワードが出た。まず「顔の見える関係が強い地域」。それは「ほかの子供をしかることができる大人がいる地域」「団塊世代のまとまりがある地域」「隣近所、せめて3軒ぐらい隣の人の顔を知っている」「あいさつができる地域」 Bグループ ・いちばん多く挙がった項目が「近所と地域」で、周りの人たちとコミュニケーションなどつながりを持つところから災害のときに強い地域になるというもの。 Cグループ ・「情報の共有」「地域の備え」「地域の中の対内的なコミュニティづくり」「地域内、外との連携」「周りの環境」というカテゴリーに分かれた。 Dグループ ・まずいちばん出たのが、「地域とのつながりがあってこそ災害に強い」ということ。 コメンテーターのまとめ ・「こんな地域が災害のときにも強い地域です」ということでは、「顔の見える地域」「備えている地域」「助け合う地域」「関係機関などと連携している地域」。「資源を生かしている地域」「自分たちの町を知っている地域」「リーダー・キーパーソンのいる地域」「学んでいる地域」「交流する地域」「情報共有、伝達度の高い地域」などのそういうキーワードが出てきた。 グループワーク2の発表 Dグループ ・私たちでできることは、地域を知ることから始めるということで、自分たちの土地の弱点であったり、自分たちの家の造られた年とか、伝承とか、いろいろ知ること。 Cグループ ・自分たちでできることというのは、各家庭の備蓄、防災に備えての家具の取り付けなど。いちばん大事なのは、ご近所でのあいさつをできる毎日。自主的にボランティアに参加していく、地域清掃に参加していくこと Bグループ ・まず自分たちでできることは、家庭内点検、家庭内備蓄、家具固定など。 Aグループ ・自分たちができることは、まず自分たちの町を知るということで、町のいいところをもう一度見付けること、町歩き、地域に友達を増やす、人と地域内とのつながりをみんなで持っていくということ。自己の知識のレベルアップ、災害が起きたときに自分の身は自分で守るために、防災訓練に進んで参加、上級救命訓練、AED講習、防災会議などを開くなどの話題が出た。 【コーディネーターのまとめ】 ・災害時は想定していなかったことがどんどん出てくる。状況に応じて臨機に対応するということがポイントになる。 |
防災とボランティアのつどい(分科会C)
内閣府(災害予防担当)
