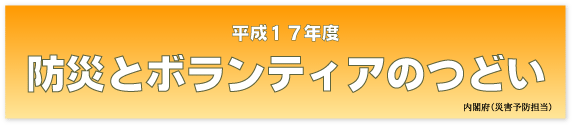
分科会B 「若者と防災ボランティア活動」
中川和之氏(NPO法人東京いのちのポータルサイト)
【関連する資料はこちらから】
グループ別に自己紹介
(取り組んでいること、関心があることを紹介し、模造紙にまとめる)
グループA
- ・神戸に送るための署名活動
- ・現在の活動:(県外)新潟県川口町の保育園で清掃
- (県内)沼津での道案内・箱根でのキャンプ-三角巾の折り方など
- ・きっかけ=けん玉がきっかけでボランティア活動に興味を持った
- ・両親は賛成、たまに一緒に参加している
- ・活動者の年齢層は4歳〜92歳
←小2で活動参加、すごい!!
←川口で幼児保育園での清掃活動を年代も近いし一緒にやった
←剣玉での石川さんの出会い=うまい! - ・スマトラ方面での防災教育⇒日本でも同じことをやっていこうと半年前から活動
- ・世田谷で防災教育づくり(1ヶ月に1度)
- ・これから別の学校にも広げていこうと考えている
- ・意見交換の場に出て情報を共有できたら、と思う
- ・早稲田の中でも他にボランティアをやっている人とこういう場でネットワークできればと思う
←これからはインターネットを作りたい
←横のつながり
←言葉がつながらなくてもやれる事がある - ・きっかけ=小学5年の時、地震を経験。ボーイスカウトの応急救護からいつのまにか防災へ
- ・年をとるにつれて日赤とも関係をもつようになってきた
- ・大学で埼玉に来たとき、SLに入る
- ・大学2年で留学(帰ってきて災害現場へ出かける)
- ・そこで日常からの防災を考える
- ・年に2回大学3年の時に横のつながりを持つためのネットワーク=防災ユースフォーラム
←大学ユースフォーラム 年2回 2泊3日 - ・30〜50人の希望者を集め、防災って?とか、防災教材を実際にやってみる
- ・事務局は持ち回り方式でやっている
- ・どの団体にも負担にならないようにしている
- ・第1回はみんなで持ちより、距離によって参加費免除
- ・第3回はソニーマーケティング ボランティアファンドから30万円の助成
- ・防災専門と教育専門がフォーラムに来て防災教育をやったり・・・
- ・継続できるような活動をしている
- ・一番成功したのは"防災教育"
- ・研究している側と地域の側で情報交換
- ・首都圏〜神戸を基本に、あとは地方から個人で参加している
- ・現場、ネット、こういう場でネットワークをつくりはじめた
- ・演習というかんじでフォーラムをやっている
- ・フォーラム内で必ず飲み会をやって意見交換をして、その後連絡のやりとりをしている
- ・紹介の紹介でネットワークは繋がるんじゃないかと思う(代替わりがやはり気になる)
- ・役割負担して弱いところをみんなで補う(自分らで資金面はどうにかやっていきたい)
←北海道出身、風邪を引いている時に震度6。布団で寝ていたら命は・・・
←6人いれば世界中誰にでも会える! - ・きっかけ=県 養成、災害ボランティアコーディネーター研修参加
- →何かできるのではないか?
- ・関西では20代、若者の参加が少ない。どう関わっていいのか?
- →狭い範囲でしか見ていなかった
- ・福井、新潟の現場へ行く(報道で見て)何のため、現場に行くのか→報道があっているのか、報道されていないところは?
- →何が大変か地元ではわからないので仮設住宅に行った(聞き取りをしたこと)
- そもそも家の大きな人たち→不満=狭い、冷たい、お風呂が狭い
- 良かった事=町に出るのが楽になった(買い物)
- ・一年後、二度目の現地。あと1年で住むことができなくなる、その後の生活が不安
- ・地区で復興住宅のわりあて21戸、希望者22戸。どう折り合いをつけるか?
- ・家に本当は帰りたいが高齢のため、雪下ろしができないのでこのまま町に住みたい
- ・問題提起
- ボランティアに雪下ろしをしてもらうので家に戻ること
- 雪下ろしが大変なので戻りたくてもこのまま町に住む どっちが良いのか?
- 高齢なのでいずれ21戸の復興住宅が全て空になる。その物件は必要なくなる
- 山間地域では広い土地は学校のグラウンドしかない
- ・たまたま災害救援の担当になった
- ・できることはやろうという事務局でもいる
- ・南郷町(宮城県地震)現場では、大分ではどうしたらいいのかということを意識している
- ・ボランティアと行政との連携。こういう場で情報交換をして、顔合わせをして情報をもらっている
- ・地域でできることはないか
- ・火事があっても、その家に住人がいるかわからない
- ・警察−未確認情報はできない。消防−警報として出す
- ・どこに行けば確実な情報を得られるか
- ・行政でも
- ・消防はボランティアを認識してくれている
- ・地域防災組織で連携は確認している
- ・資材は外部から車で土木事務所持っているものを使う
- ・同じ活動でもお金をもらえるものともらえないものがある
- ・ボランティアに労力を、事務局としては資材、資金調達をすると申し合わせている
- ・根回しとかもやっておく、こういう時はよろしくねっていう
- ・被災者支援金、ボランティア活動資金の二本立てで募金をつのった
- ・日常のボランティアの活動に防災を組み入れる
グループB
- ・少年時代公害がすごかった
- ・環境全体で考えていかないといけない
- ・防災だけではなく環境も一緒に考えよう
- ・日常の中に非日常に備えないといけない
- ・危ない家を知ることで、情報を共有する
- →マップを作って危ない家の人を早く助けられるように、早見まわりマップを作った
- ・大学生と一緒に活動している
- ・高校生とのつながりを作りたい
- ・行政のサポートを得ながら活動した
- ・防災教育のノウハウの支援活動
- ・以前はボランティアは特別な存在だった
- ・今は社会の一員として子供も頑張らないといけない
- ・防災教育をやっているところが少ない
- ・もちもち募金−気持ち、おもちを贈る募金
- ・よさこい東海区等
- ・保育園でのボランティア−小さい子の世話、掃除も遊びになる
- ・4、5年生のとき、神戸へ(被災者の話、荷物の落下→地震のこわさを感じた)
- ・きっかけ=友だちの誘い
- ・印象的なこと=新潟に倒壊している家屋→東海地震が来たら・・・
- ・「ありがとう」の言葉、クラスの友だちにいろいろ教えること
- ・大人になったら、子供にできない活動をしたい
- ・子供じゃないとできないことは?高齢者−子供になら話せることもある、心の支え。もっと積極的に
- ・子ども対象の防災キャンプ(5回目)−被災時の避難体験(2000年〜)
- ・街あるき−「防災」という視点を持って歩いてみよう→損保協会
- 自分の街で「防災」を学ぶ。教える側(大学生)にも学びが成立
- まちの人との「つながり」づくり(EX:パソコンのおじちゃん)地球を担うのは「子どもたち」
- ・MAPづくり−不審者、濃煙体験、新宿区などで。子どもたちの「発表会」−家庭での防災を考える場を
- ・対象−中・高生にも広げたい
- ・小・中・高・大のつながりをつくりた
- ・将来は地元(地域)にも還元したい
- ・まっちワークグループ・・・30人位子どもと共に疑問を持つ「まちづくり」が原点
- →将来は地方行政に生かしたい
- ・消防の外部団体(50人位)
- ・CPR・ロープワーク・消火器の使い方
- ・社会奉仕−ミュージックベルなど→高齢者
- ・イベント−クリスマス会、キャンプなど
- ・月1〜2回の活動・・・消防署で
- ・行政から指導方針があり進めている
- ・消防士をめざすボランティアリーダー
- ・AED(徐細動機)の紹介
- ・防災ゲーム研究会−カードを用いて行うゲーム(EX:双六、防災ダック)
- ・教育関係者も参加
- ・自分のまちの防災力向上
- ・人間形成をめざす向きもある
グループC
- ・「災害を伝える」
- ・外部講師・フィールドワーク(六甲山・消防学校)
- ・ボランティア−普通科とも協力、雪かき
- ・進路−公務員、福祉
- ・1995年和歌山佐移住の祖父母が被害、校外学習、実体験 →震災を伝える母親になる
- ・応急手当の普及
- ・動機=救急救命士 学生が応急手当ができたら命が助かる、命をどう守るべきか
- ・若者−学生生活の中でどのように身につけるか
- ・少年犯罪に興味(動機=怪我を伴う)
- ・AEDをきっかけに心肺蘇生法
- ・メンタルケアと応急手当
- ・ボランティア自身の健康管理
- ・年齢にあった教育!
- ・三宅島ボランティアに参加(2000年〜)−情報発信(情報誌)
- ・在京三宅島会の手伝い
- ・三宅島をテーマに修士論文を作成する←公的支援打ち切り、問題提起
- ・茶道クラブを利用してボランティア
- ・小学生からボーイスカウト(救急法、キャンプ)−おもしろいから
- ・大学で火山
- ・1977年 有珠山(北海道)噴火、噴火前に現地へ
- ・兵庫県に帰ってきて15年、特に災害がなかった、そして阪神大震災
- ・理科の教師として伝えることがある
- ・1996〜1999年 学生の震災体験をネットで
- ・小中高の理科や保健で教えること、震災を伝える
- ・ボランティア活動=地震や火山のサマーセミナー:今までのネットワークから様々な人に助けられる
- ・ボランティアは自分でできることを、できる範囲で
- ・スポーツ中心の生活(サッカー)
- ・ボランティアへのきっかけ=大阪のNPOの人−子育て→防災→ボランティア
- ・いろんな人と話す
- ・いろんな所にいく
- ・勉強になる、ネットワークが広がる
- ・たくさんのNPOがある(1000)
- ・得意分野をいかす
- ・自分のネットワークを広げましょう!!
グループD
- ・消防士の夢
- ・豊岡に初めて参加、乗り気じゃなかったがおじいちゃんが泣きながら感謝してくれた
- ・楽しい防災−楽しくないと人は集まらない、知っていれば助けてくれる
- ・被災地に行くだけがボランティアじゃない。でも現地は困っている。行きたくなった。記事を見た次の日から活動
- ・帰ってから次に活かそうと思って、防災ガイドブックを作り感心が集まった
- ・自分が知っていたボランティア=高齢者、障害者・・・しかし、災害ボランティアもある
- ・大学にボランティアサークルを作った
- ・最初は2人、他の大学生は興味を持ってくれなかった
- ・よく分からないけど、おまえが言うんならボランティアに一緒に行くか(信頼感)
グループE
- ・小学校の時から防災・人の力になれることを学んだ
- ・ボーイスカウトの指導を通じてさらに活動が強まった
- ・長崎県雲仙普賢岳、噴火災害に始まり今日に至った
- ・災害地での子ども達の活躍に注目して、少年防災ボランティア、内閣府からたっぷりお金をもらった
- ・災害ボランティアの役割−被災者への日常の確保
- ・不足分を補足すること
- ・中学生の防災マップを通じた、地域の備え、年代を通して話し合い、地域の実状を知る。マップへの書き込み、際が時の若者の役割
- ・にいがた発信防災ネット−中越地震を機に発足。何ができるのか、長期的
- ・学習支援ボランティア(学習の遅れに対応)教育委員会を通して授業のフォロー
- ・ボランティア活動を続けることの大切さを知った。顔見知りになった。交流が大切
- ・現在名古屋に在住、新潟のことを伝える
- ・若者の防災意識向上、消防の取材を通じた意識付け
- ・新潟の体験を伝えたい
- ・防災リーダーとして、とっさの場合動けるような備え
- ・静岡県沼津
- ・中学生からボランティアとして神戸へ。被害の様子を見た
- ・行くことは大切だが、地域の人々に知らせる、自分にできること
- ・助けようとする気持ちより「お手伝いしたい」という心、被災地の方も自分
グループF
- Fグループ
- ・小学2年生の時阪神大震災に遭う
- ・高校生の時放送クラブに入っている。ラジオ・TV作成
- ・震災の事をみんなに伝えたい→2004年「NHK全国高校コンテスト出品」
- ・台本や音をリアルにしたかった。苦労したが楽しくやれた
- ・「TVドキュメント作成(全国3位)」
- ・一日一日を大事にしたい
- ・これから活雄をしていきたい。メディアの仕事をしたい
- ・まちづくりのサークル
- ・東京に1人ぐらい(商店街が主)
- ・大学のサークルの中、大体活動している
- ・防災キャンプ(夏休み、防災体感をしながら)
- ・まちをよく知る、小学生達とまち歩き
- ・防災マップ−年3〜4回。祭りに参加
- ・消防団に入る−消火活動の練習(ポンプ車)
- ・そこに住んでいるから、地域の活動に参加
- ・エネルギー関係の仕事をしたい
- ・海外、国際協力もした←学生時代に活動
- ・災害が起こってから活動した。大型バスに乗って
- ・防災の点は?衣・食・住、考えて行かなければならないと思っている
- ・学生の力でボランティアをしている
- ・村おこし、NPO立ち上げたい。2〜3年
- ・学生を呼び込んで雪下ろしを考察中(1日はボランティア、もう1日はレジャー)
- ・学生の力(マンパワー)で災害ボランティアをしていきたい
- ・大正生まれ
- ・海難事故→船が波に揺られ、普通の3倍の時間
- ・雪害
- ・河川の氾濫→床上浸水・・・過去の話だが、今は良い世の中になった
- ・強盗被害
- ・火事←天ぷら油
- ・消防団−作文が全国で受賞
- ・東京大空襲−防空壕にまで火の粉・煙、父は背中をやけど、母は半狂乱
- ・これら災害の様子を絵・文・写真として保存。自分の体験を伝えている
- →若い子に託している
- ・現地のボランティアに行けず募金
- ・名古屋での水害寺、バイクでの支援が役に立った
- ・子どもの頃、家が2階まで浸水、自衛隊に救助される→今の根底にある
- ・オートバイの世間のイメージ=うるさいetc.
- →でも、自分の好きなこと 自分の好きなことでボランティアできると良い
- ・自慢ではなく、自分の視野を広げるために
- ・地方ごとの情報のネットワークを広げる
- ・ひとりひとりの得意分野の強み−協力
若者の防災ボランティア活動宣言
- 自己紹介と意見交換のあとに、各グループの若者が「こんなことをしていきたい」という宣言をまとめる。
グループA
- ・私たちはこれからも防災の輪を広げていきたいと思います。
- ・なぜなら少しでも多くの人がいろいろな経験や知識を持ち寄って防災について考えることが大切だと思うからです。
- ・その防災の輪を広げるうえでは、ここにいらしゃっている皆さんそれぞれ素晴らしい人脈、人の輪を持っていらっしゃると思います。上に座られているかたから後ろで聞いているかたまで地域コミュニティ、学会、それぞれ皆さんご自身のネットワークがいろいろあると思いますので、その人の輪を僕たちのような若い人間にぜひ譲っていただいて、いろいろな場で紹介をしていただきたいと。また、僕たちのような若い人間がこういう場に来ますと、皆さん、スーツでいらっしゃっていて、僕はどうしたらいいのだろうというようなことになりかねませんので、懇親会があるようなイベントなどでぽつんと立っている若者がいたらぜひ声をかけていただきたいと切実に思っています。
グループB
- ・私たちは人のつながりを作っていきます。それは地域で助け合うためです。そのためにぜひ皆さん、今日から隣の人の名前をちゃんと覚えてください。
- ・私たちは防災教育をしていきます。それは一人一人の防災意識を高めたいからです。そのために皆さんの専門知識を貸してください。
- ・私たちは若者でないとできないことをしていきます。それは無邪気な笑顔があるからです。そのために私たちに何でも仕事を任せてください(拍手)。
グループC
- ・私たちは学校教育に防災、命を取り入れる活動をしていきます。それは幼いころから実体験をすることが大切だからです。そのために皆さんの国家を動かす国民の力を貸してください。
- ・私たちは自分のできることをしていきます。それは長続きの秘訣だからです。そのために皆さんのネットワークの力を貸してください。
- ・私たちは震災を伝える親になります。それは震災を風化させないためです。そのために皆さんの経験の力を貸してください(拍手)。
グループD
- ・私たちは災害で傷ついた子供たちと野球がしたいです。
- ・私たちはいろいろな人と出会いたいと思います。
- ・私たちは災害によって亡くなる人を一人でも減らしたいと思っています。
- ・なぜなら、スポーツを通じてその子供たちを励ましたいからです。
- ・なぜなら、いろいろな人と出会うことによって、これまで新しい一歩がいろいろ踏み出せたからです。
- ・ なぜなら、助かった一人が世界でたった一人だけだからです。そして、その三つすべてをかなえるのがだれかを思う皆さんのその気持ちを私たちに貸していただきたいと思います。以上です(拍手)。
グループE
- ・私たちはボランティア活動を伝えていきます。それは子供たちのボランティア活動につながるからです。そのために皆さんの知識と経験を私たちに貸してください。
- ・私たちは同世代に楽しい防災知識を向上させていきます。それは、これからの日本を支えていくからです。そのためには皆さんの多大なるお力をお貸しください。
- ・私たちは今までの活動を通してたくさんの人と会うことができました。そして、私たちはこれからもたくさんの人に会いに行きます。なぜならば地震によって被害を受けた人、復興に取り組む人、防災に意識している人、そして、すべての人に会ってつながりを持つことが将来の減災につながると信じているからです。そのために皆さんも私たちに会いに来てください。
グループF
- ・私たちは一生懸命生きています。それは一日一日を大事にしたいからです。
- ・そのために皆さんお互い助け合ってください。
大人からのメッセージ
私たちは若者に期待しています。自分の意思で自分にできることを自分らしく続けていってください。分科会B大人一同。
内閣府(災害予防担当)
