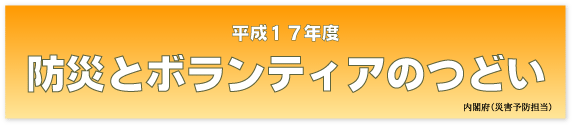 |
| 分科会A 「被災地が主役の防災ボランティア」 コーディネーター 丸谷浩明 氏(京都大学経済研究所教授) 午前中活動報告者からの補足説明 ?愛媛県新居浜市 (災害ボランティアセンターの取り組み) ・8月中旬と9月末の台風被害では、住民だけではなく、行政との関係も大きく変わった。当初から、災害ボランティアセンター(以下センター)では災害ボランティア、自治会関係者、行政職員と一緒に毎日ミーティングを行っていた。9月の台風災害直後には、センターと行政の間で行政からセンターに対する要望、またセンターから行政への要望、行政から住民への依頼事項などを確認した。行政がその2日後、行政の対応と担当課を整理した文書を作成して新居浜市内連合自治会の会長を対象にした説明会を開催し、住民への要望も伝えた。 (立川地区の取り組み) ・地域に避難のことをチラシなどによる一方的告知ではなく、意思表示ができるアンケートや集会で声を聞きだすことができたため、地域の実情を知ることができ、結果的に避難がスムーズにできたと思う。 質疑応答 ■ボランティア保険に加入していない災害ボランティア活動の対応をどうされたのか ?宮崎県宮崎市 ・午前中に復興支援のためのフリーマーケットを開催したと話をしたが、その売上は県の共同募金会に全額寄附している。フリーマーケットの物品は、マスコミ関係者の協力を得て新聞等で呼びかけをした。 質疑応答 ■けがや日射病があったということですが、狂犬病とか重大な病気はあったのでしょうか。防災ボランティアの安全衛生マニュアルをつくっているので参考にしていただきたい。 ?山口県美川町 ・災害発生時、東西南北に長い美川町の地形が、大体二分された状態になった。迂回路も土砂崩れのために地域が陸の孤島化し、人口1700人、850世帯のうち172戸の床上浸水、床下が92戸という被害状況だった。 質疑応答 ■高校生にはどのように呼びかけたのか。 【3地域に対しての意見交換】 ■新潟県中越地震の経験から、地元に社協職員やボランティアに参加できる方がほとんどいない地域も多いと思う。やはり地元で、ボランティア活動を十分経験した人がいることは大きな違いだと思う。外部の応援団との関係で困った点や克服した点について教えていただきたい。 フリーディスカッション ?除雪ボランティア活動について ■昨年末ぐらいから雪害がひどくなり、除雪ボランティアが大勢参加するようになっているが、その安全衛生対策を心配している。「雪氷災害調査検討委員会」がホームページをつくっているが、衛生対策はほとんど着手されていない。除雪作業は重労働のため、心臓病や脳卒中などが心配される。被災地で自主的に取り組んでいる例があれば、教えていただきたい。 ?大規模災害の対応について ■大規模な災害が起こった場合、都道府県単位や市町村単位での対応というのは検討されているのでしょうか。地域によっては重化学工業や発電所などの非常に危険な地域もあるため、どのような対処が検討されているのか。また、そのような場合のボランティアセンターの運営は個別に検討されているのか。 ?復興期のボランティア活動 (話題提供)長岡市の仮設住宅近くでお茶飲みサロンを開き、被災者との話す機会からニーズを見出すような形で、被災者の声を取りまとめた。2005年12月からは足湯マッサージとお茶飲みサロンを仮設住宅の集会所で行っているが、その中で、ボランティア活動へ依存しているように感じている。新潟県中越地域ではこれから被災者が主体性を持って団結し、復興していくことが望まれる。地域外からのボランティアはいずれ離れなければならず、ボランティアセンターや社協などとつながりをもって、新しい活動を見出していかなければならないと感じている。地域を重視したボランティア活動や、地域のメッセージをうまくひき出せるしくみづくり、地域の人々と仮設住宅の人々をつなげる役割を果たしていきたいと考えている。 ?地域コミュニティ活動とボランティア活動の接点 (参加者・コーディネーターからの発言) |
防災とボランティアのつどい(分科会A)
内閣府(災害予防担当)
