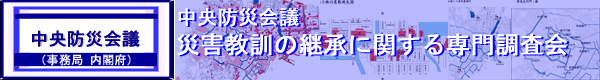災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成16年3月
1855 安政江戸地震
報告書の概要
-
第1章 安政江戸地震
(地震動)
安政2年10月2日(1855年11月11日)、午後10時頃発生した地震。古文書に基づき各地の震度を推定。震度5以上の主な場所は以下の通り。
・震度6以上:東京都内→千代田区丸の内、墨田区(本所)、江東区(深川)
周辺地域→取手市、幸手市、浦安市、松戸市、木更津市、横浜市(神奈川区)
・震度5 :東京都内→中央区日本橋・銀座、千代田区霞ヶ関・永田町
周辺地域→水戸市、市川市、佐倉市、富津市、川崎市、横浜市(鶴見区)、藤沢市
(地盤と揺れ)
震度5以上のポイントを地図上に示すと、関東平野の東側はほぼ円形に、西側には大きくくびれた曲線となる。これは、関東平野の西側の多摩丘陵から丹沢山地にかけて固い地盤が分布するためである。
(火災の発生)
火災の発生場所は、揺れの強いところとほぼ対応。風が弱かったため全焼失面積は1.5平方キロ程度(関東大震災は約38平方キロ)。 -
第2章 災害の社会像
(被害状況)
江戸市中の死者数1万人前後。
大名屋敷は、266家のうち116家で死者が発生。特に、大名小路(現在の丸の内辺り)にあった55家のほぼ全てが何らかの被害。
旗本・御家人の死傷者数は不明。建物の被害は全体の約80%と推定。
町人地の家屋は1万4000余軒が倒壊(特に深川で大きな被害)。
(幕府の緊急対応)
発災直後から情報収集を実施。また、発災2日目から以下のような取り組みを開始。
・市中取締り(巡視)の実施
・死者の無料埋葬
・米の配給
・物価抑制のための公定上限価格の設定
・義捐金の報奨 など
(災害復旧事業)
以下のように進捗。
・玉川上水では、安政5年で一応修復
・役宅(現在の中央官庁)は安政6年にほぼ修復終了
・江戸城の見附門・橋、市中の橋などは、発災後2〜3年かけて修復終了。白石垣は修復を継続。 -
第3章 地震と人びとの想像力
(庶民の対応)
庶民が安政江戸地震をどのように受け止めたのかということを当時の庶民の心情が描かれた地震鯰絵を使って説明。31枚のカラー絵図が収録された絵図集。 -
まとめ −安政江戸地震と現代の防災−
南関東地域において発生した最大の直下地震である安政江戸地震を現代に投影し、来るべき都市直下地震への備えを検討。
・地盤が軟弱な日比谷から丸の内周辺の被害が大きかったが、現代の東京は軟弱地盤上に広範に展開しており、建築物の耐震性の向上を図ることが緊急を要する課題
・江戸幕府では、緊急時の対応マニュアルを備えていたため、発災後に迅速な対応が可能であったことを踏まえ、防災行政担当者向けの行動マニュアルの整備と人材育成が重要
・当時の江戸の町人は共助・自助を中心に心をひとつにして困難を乗り越えてきており、こうした取り組みは時代を超えた共通の課題 -
<広報「ぼうさい」>
シリーズ「過去の災害に学ぶ」(第7回): 広報「ぼうさい」(No.33)2006年5月号、12-13 (PDF形式:1.4MB)
 ページ
ページ
報告書(PDF)
 表 紙
表 紙 目 次
目 次 はじめに
はじめに 第1章 安政江戸地震
第1章 安政江戸地震 第2章 災害の社会像
第2章 災害の社会像 第3章 地震と人びとの想像力
第3章 地震と人びとの想像力 まとめ −安政江戸地震と現代の防災−
まとめ −安政江戸地震と現代の防災− 参考文献等
参考文献等 奥 付
奥 付