三宅島火山ガスに関する検討会
中 間 報 告
目 次
1 はじめに * 2 三宅島火山ガスの状況 *1 はじめに
平成
12 年 6 月に始まった三宅島の火山活動は、同年 8 月の最大規模の噴火に続いて火砕流が発生したことから、全島民は島外への避難を余儀なくされた。その後、有害な二酸化硫黄などを含む火山ガスを、世界にも類を見ないほど大量に放出するようになった。この島民の帰島を阻害する大きな要因となった火山ガスの放出はいまだに続いており、避難生活も 3 年目を迎えている。その一方、火山ガスの放出がおさまった場合にはすみやかに帰島できるよう、島内では砂防ダムなどの防災施設の建設や道路・港湾施設の補修工事に加え、水道施設や電気設備などライフラインの復旧が着々と進められている。
また、火山噴火予知連絡会は、最近の観測データから火山活動は全体としてゆっくりと低下し、それによって火山ガスの放出量が減少してきたとの見解を示している。
そこで、火山ガスがどのような状況になれば帰島が可能になるのか、安全確保対策などの面から科学的に検討するため、東京都と内閣府は共同して三宅島火山ガスに関する検討会(以下「検討会」という。)を設置し、以下の事項を検討することとした。
( 1 )三宅島の火山ガスの現状分析等に関すること
( 2 )火山ガスが人の健康に与える影響に関すること
( 3 )火山ガスに対する安全確保対策に関すること
( 4 )三宅島への帰島の判断材料に関すること
( 5 )その他必要な事項
これまで
3 回開催された検討会では、主に( 1 )について検討を重ね、噴火直後から現在までの二酸化硫黄などの火山ガスや気象などの観測データを、様々な視点から解析してきた。今回の中間報告は、この解析の結果得られた島内の火山ガス濃度分布や気象との関係について、二酸化硫黄を中心にまとめたものである。
一般に火山ガス成分の
90% 以上は水蒸気である。そのほかに二酸化硫黄、硫化水素、塩化水素、二酸化炭素など人体に有害な成分が含まれる。
(
1 )二酸化硫黄( SO2 )二酸化硫黄は無色で刺激臭のある気体で、比重は
2.26 (空気は 1 )であり、空気よりも重い。低濃度でも呼吸器や眼、喉頭(ノド)などの粘膜を刺激し、高濃度の状態では呼吸が困難になることがある。また、ぜん息や心臓病などの疾患があると、健康な人が感じない低い濃度でも、発作を誘発したり増悪させることがあるため注意が必要である。三宅島では、現在も大量の二酸化硫黄の放出が続き、島内でも常時観測を続けている。帰島を阻んでいる最大の原因の一つである二酸化硫黄濃度の現状把握と健康・安全確保対策が重要である。
なお、二酸化硫黄には環境基本法に基づく環境基準が定められており
・
とされている。
(
2 )硫化水素( H2 S )硫化水素は、無色で、火山地帯や温泉などで臭う卵の腐ったような臭いの気体であり、比重は
1.19 で空気よりやや重い。高濃度となると人体に影響を及ぼす。三宅島では、現在島内で観測が行われている。
(
3 )塩化水素( HCl )塩化水素は無色、刺激臭のある気体で、比重は
1.27 で空気よりやや重い。湿っていると腐食性が強く、比較的低濃度でも目、皮膚、粘膜を刺激する。三宅島では、塩化水素濃度は直接観測されていないが、火山ガス中の全硫黄量の 10 分の 1 程度である。また、降水中の塩素イオン量は火山ガスの影響によりやや高くなっている程度である。
(
4 )二酸化炭素( CO2 )二酸化炭素は、無色、無味、無臭の気体である。高濃度になると、酸素欠乏を起こす場合がある。バックグラウンド(通常の大気)の濃度が約
375 ppm であり、ビルなどの室内環境の基準は 1,000 ppm である。三宅島では、噴煙中の SO2 濃度が 25 ppm 時に CO2 濃度が約 414 ppm という観測結果が得られている。
(参考:岩波書店「理化学辞典」ほか)
これまでの検討の中で、以下の物質については、二酸化硫黄と同様に人体に影響を及ぼすことが指摘され、現在三宅島島内における濃度等を測定しているところである。その結果を踏まえ、安全対策の必要性等について検討することとしている。
(1)
硫酸ミスト 硫酸ミストとは、火山ガス中の二酸化硫黄が、大気中において微細な浮遊粒子の表面をおおっている水の膜に溶け、紫外線による光化学反応によってさらに毒性の強い三酸化硫黄となったものである。
いわば「硫酸の霧」ともいえ、皮膚、粘膜への腐食性、刺激性が強く、吸引すると特に呼吸器系に刺激を与え、慢性の上気道炎又は気管支炎の原因となり、二酸化硫黄と同様、またはそれ以上に人体や環境に影響を及ぼす。
(2)
浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質とは火山灰などからなる、一般に
10 マイクロメートル以下の粒子状物質のことで、呼吸器系や循環器系に影響を及ぼす。また、これらの物質中に付着した重金属についても吸入した際の健康影響が懸念されており、火口内で沈着し山麓に影響はないとする見解もあるが、確認のため重金属量についても測定を行う。
浮遊粒子状物質については環境基準が定められており
・
とされている。
(参考:環境省「環境白書」、東京化学同人「環境科学辞典」)
二酸化硫黄(
SO2 )濃度については、以下の図に示すとおり、気象庁が 6 点(電気化学式)で、東京都、内閣府、三宅村(以下「東京都等」という)が 10 点(紫外線蛍光法)で観測を行っている。硫化水素( H2 S )については、東京都が 5 点(定電位電解法)で観測を行っている。
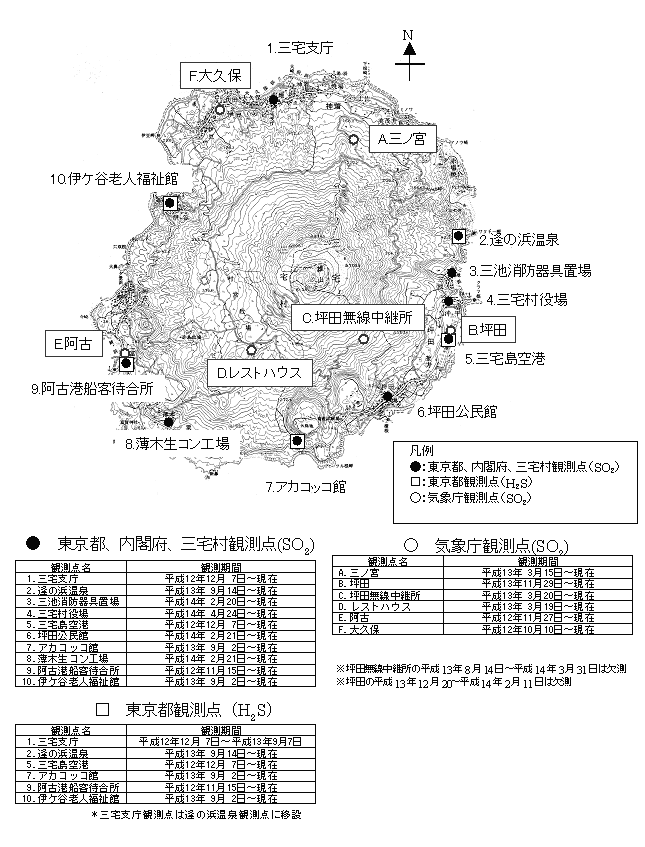
※観測機器・原理の違い
二酸化硫黄濃度の固定観測では、気象庁が電気化学式、東京都等が紫外線蛍光法という異なった方式により観測を行っている。これらの方式は、それぞれ火山噴火口の周辺の高濃度観測、生活空間の環境濃度の測定を主な目的としている。また、測定原理が異なるため、濃度変化に対する応答の速さや火山ガスに含まれる他の成分の影響による誤差の大きさが異なっている。このため、本報告では、本来の使用目的に沿って、山麓部については紫外線蛍光法によるデータ、山腹部については電気化学式によるデータを解析することとした。
|
| 気象庁 | 東京都等 |
測定方式 | 電気化学式 | 紫外線蛍光法 |
使用目的 | 火山活動状況の監視 | 環境基本法及び大気汚染防止法に基づく大気汚染の監視 |
原理 | 隔膜を透過した二酸化硫黄が電解液中に溶解し、電解液が酸性になることを利用して検知する。 | 紫外線を二酸化硫黄に照射して発した蛍光を計測する。 |
測定範囲 | 1 〜 150 ppm | 0.02 〜 20 ppm |
測定精度 | 1 〜 5 ppm ± 1 ppm5 ppm 以上:指示値の± 20% 以内 | フルスケールの± 1% 以内 |
表示分解能 | 1 ppm | 0.02 ppm |
1 時間値等の測定法 | 2 分ごとの瞬間値をもとに 1 時間値を算出している。 | 連続測定データをもとに、 5 分毎、 1 時間毎の平均値を算出している。 |
二酸化硫黄濃度については固定観測点のほかに、内閣府、三宅村が 20 点で可搬型の観測器(定電位電解法)を用いて観測を行っている。
また、気象庁が、決められた 25 地点で、午前 9 時ごろ島内を周回してガス検知器(定電位電解法)により観測を行っている。
なお、内閣府、三宅村の観測器は、電気化学式と同様に火山活動状況の監視の目的に使用可能であり、かつ、紫外線蛍光法とよい相関を得ている。
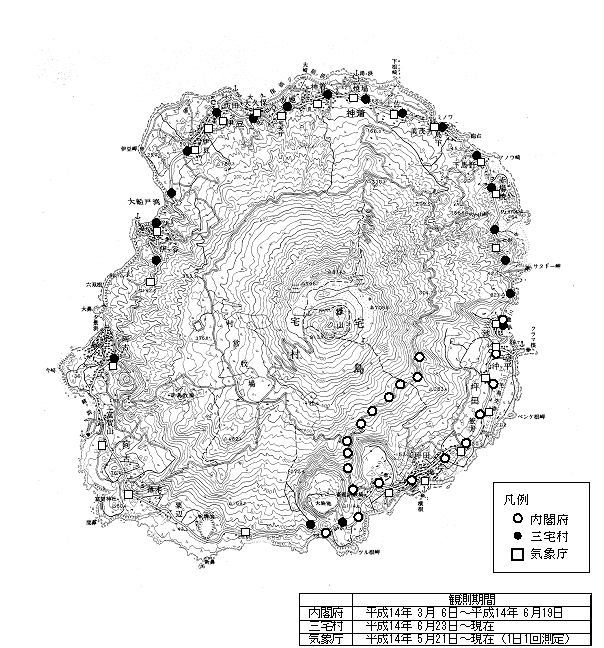
2.4 二酸化硫黄濃度観測データの解析
二酸化硫黄濃度の観測データを解析するに当たり、以下の基準値等を参考にした。
(1)
環境基準 環境基本法に基づき、「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として定められたもの。
(2)
許容濃度通常の労働(
1 日 8 時間、週 40 時間程度で肉体的に激しくない労働)で、当該物質(今回の場合は二酸化硫黄)の平均暴露濃度(呼吸保護具を装着していない状態で吸入するであろう当該物質の濃度)がある数値以下であればほとんどの労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度。米国の ACGIH が勧告している許容濃度: 2 ppm
注) ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 米国産業衛生専門家会議
(3)EPA
の短期曝露の指針値行政が介入すべきレベルとして、
5 分値( 5 分値とは、 5 分ごとの平均濃度)で以下の基準が設けられている。0.6 ppm 「懸念レベル」
2.0 ppm 「危険レベル」
注) EPA : Environmental Protection Agency 米国環境保護局
解析は、気象条件の季節変動の影響も考慮して、観測開始から
なお、グラフ中の 0.0 ppm は、検出限界以下のことである。
(1)
各観測点の濃度の推移( 1 時間値)三宅島島内の二酸化硫黄濃度の推移を知るため、各観測点における観測開始から平成
14 年 10 月 31 日までの、 1 時間値の推移をまとめた( 図 1 、 2 )。図 1 は山麓の観測点、図 2 は山腹の観測点である。また、可搬型の観測点における 1 時間値の推移についてもまとめた( 図 3 〜 6 )。
結果:
島の東部では観測開始以降、比較的高濃度の二酸化硫黄が観測されている(
火山ガス噴出口に近い山腹の観測点では 20 ppm を超える高濃度の二酸化硫黄が観測されている( 図 2 )。
島内の濃度分布を見ると、東部から北部にかけて、また、東部から南部にかけて、濃度の状況は徐々に低くなる傾向である( 図 3 〜 6 )。
(2)
累積濃度分布( 1 時間値)一般環境と比較するため、平成
13 年 8 月 1 日から平成 14 年 7 月 31 日までの 1 年間のデータについて、三宅島の 3 観測点と東京都大気汚染常時監視測定局の 3 観測点の累積濃度分布をまとめた( 図 7 )。結果:
都市部の累積濃度分布は対数正規分布に近いと考えられるが、三宅島は明らかに異なっている(
(3)
濃度階級別出現頻度( 1 時間値)観測期間が
1 年以上ある 6 観測点における平成 13 年 11 月 1 日から平成 14 年 10 月 31 日までの 1 年間について、どの程度の濃度になることが多いのかを見るため 1 時間値の濃度階級別出現頻度をまとめた( 図 8 )。また、同じ 6 観測点について、平成 13 年 1 月 1 日( 3 観測点は平成 13 年 10 月 1 日)から平成 14 年 9 月 30 日までの 21 ヶ月間について、 3 ヶ月ごとに 1 時間値の濃度階級別出現頻度の推移をまとめた( 図 9 )。
結果:
島の東部では高濃度となる頻度が高い(
3 ヶ月ごとの濃度階級別出現頻度の推移を見ると、観測点によって高濃度の観測される季節が異なっているが、全体的には高濃度になる頻度は減少している( 図 9 )。
(4)
濃度階級別出現頻度(日平均値)環境基準を目安として評価するため、観測期間が
1 年以上ある 6 観測点における平成 13 年 11 月 1 日から平成 14 年 10 月 31 日までの 1 年間の日平均値について濃度階級別出現頻度をまとめた( 図 10 )。結果:
二酸化硫黄の日平均値についても、島の東側では
比較的濃度の低い三宅支庁においても 0.04 ppm を超える日の割合が 7% 程度であり、環境基準と比較するとまだ高い値を示している( 図 10 )。
(5)
風向・風速別濃度分布( 1 時間値)観測期間が
1 年以上ある 6 観測点における平成 13 年 11 月 1 日から平成 14 年 10 月 31 日までの 1 年間について、風向と風速による影響を見るために、 1 時間値を風向・風速別に表示した( 図 11 )。※解析に使用した風向・風速データについて
風向・風速のデータは、現在観測されている風向等のデータのうち、三宅島雄山山頂付近の風にもっとも近いと考えられる八丈島高層気象(
結果:
風と濃度の関係では、観測点から噴出口を望む方向から±
(6)
風向を考慮した平成 13 年と平成 14 年の濃度階級別出現頻度( 1 時間値)観測期間の長い
3 観測点について、放出量と濃度の関係を見るため、放出量の異なる平成 13 年と平成 14 年の平均値、最高値、濃度階級別出現頻度を比較した。この際、風下になりやすい 2 ヶ月間(観測点により異なる)の、風下となった時間のデータのみを抽出した( 図 12(PDF形式:191.6KB)なお、三宅島空港観測点については比較のため、風下でないとき(南西風)についても分析した。
結果:
平均値については、平成
(7)
濃度の日内変動( 1 時間値)観測期間が
1 年以上ある 6 観測点における平成 13 年 11 月 1 日から平成 14 年 10 月 31 日までの 1 年間について日内の濃度の傾向をみるため、 1 時間値の最高値、平均値( 図 13 )と、濃度階級別出現頻度( 図 14 )をまとめた。結果:
平均値の日内変動をみると、比較的高濃度となる三宅島空港観測点では夜間の方が高濃度となる傾向があるが、全体としては顕著な傾向は見られない。最高値や高濃度の出現頻度は、時刻別に顕著な傾向は見られない(
(8)
降雨時の濃度階級別出現頻度( 1 時間値)観測期間が
1 年以上ある 6 観測点における平成 13 年 11 月 1 日から平成 14 年 10 月 31 日までの 1 年間について、降雨の有無による濃度の傾向を比較するため、島内 4 ヶ所の全アメダス観測点で 1mm 以上の降雨が観測され、かつ風下側となったときと、降雨のない風下側となったときの濃度階級別出現頻度をまとめた( 図 15 )。結果:
降雨と二酸化硫黄濃度の関係については、アカコッコ館観測点を除き、降雨があると濃度が減少する傾向がある(
(9)
噴出口および火口縁からの距離と濃度( 1 時間値)観測期間が
1 年以上ある 6 観測点における平成 13 年 11 月 1 日から平成 14 年 10 月 31 日までの 1 年間について、風下側となったときの 1 時間値の最高値及び平均値と噴出口や火口縁からの距離との関係を解析した( 図 16 )。また、風速が 7 m/s 以上のときの平均値についても解析した。また、山腹と山麓を比較するために同様の条件で気象庁の 6 観測点のデータ(電気化学式によるデータ)を用いて解析した( 図 17 )。
結果:
噴出口からの距離と二酸化硫黄濃度の関係については、噴出口からの距離が遠くなるにつれて、観測される二酸化硫黄濃度は概ね小さくなっている。アカコッコ館観測点については、比較的噴出口から近いものの濃度は低い傾向である。火口縁からの距離と濃度の関係については、顕著な傾向は見られない(
(10)5
分値における濃度別超過頻度の推移濃度の短時間変化を見るために、各観測点における観測開始から平成
14 年 10 月 31 日までの 5 分値の 0.6 、 2 、 5 ppm の濃度別超過出現割合をまとめた( 図 18 )。結果:
(11)5
分値 2 ppm および 5 ppm の超過継続時間の推移各観測点における観測開始から平成
14 年 10 月 31 日までの 2 ppm および 5 ppm の超過継続時間(連続してその濃度を超える値が観測された時間)を時間別にまとめた( 図 19 、 20 )。結果:
(12)
高濃度観測時における短時間濃度変化( 5 分値)高濃度がどのような時間変化で現れるのかを知るため、各観測点において平成
14 年 10 月中に 5 分値で最高濃度を観測した時刻を中心に 24 時間の濃度変化を示した( 図 21 )。結果:
高濃度観測時における短時間濃度変化を見ると、高濃度の出現頻度が低い地域でも、急激に高濃度となることがある(
硫化水素は、二酸化硫黄と同様に人体に有毒なガスである。
そこで、島内の濃度推移を知るために硫化水素を測定している東京都の
その結果、島の東部での値が相対的に高くなっているものの、許容濃度 :10 ppm (日本産業衛生学会、 ACGIH )と比較すると低い値で推移している。
また、過去の観測データをみても、最高濃度は 2.9 ppm と許容濃度を大きく下回っている。
図 2 1 時間値の推移(山腹の観測点)
図 3 1 時間値の推移(可搬型観測点 1 )
図 4 1 時間値の推移(可搬型観測点 2 )
図 5 1 時間値の推移(可搬型観測点 3 )
図 6 1 時間値の推移(可搬型観測点 4 )
図 7 累積濃度分布( 1 時間値)
図 8 濃度階級別出現頻度( 1 時間値)
図 9 濃度階級別出現頻度( 1 時間値、 3 ヶ月ごと)
図 10 濃度階級別出現頻度(日平均値)
図 11 風向・風速別濃度分布( 1 時間値)
図 12 風向を考慮した平成 13 年と平成 14 年の濃度階級別出現頻度( 1 時間値)(PDF形式:191.6KB)
図 13 濃度の日内変動( 1 時間値、最高値、平均値)
図 14 濃度の日内変動( 1 時間値、濃度階級別出現頻度)
図 15 降雨時の濃度階級別出現頻度( 1 時間値)
図 16 噴出口および火口縁からの距離と濃度( 1 時間値、山麓)
図 17 噴出口および火口縁からの距離と濃度( 1 時間値、山腹)
図 18 5 分値における濃度別超過頻度の推移
図 19 5 分値の 2 ppm 超過継続時間の推移
図 20 5 分値の 5 ppm 超過継続時間の推移
図 21 高濃度観測時における短時間濃度変化
図 22 硫化水素濃度の推移( 1 時間値)
3 考察
以上のような解析結果及び現地の観測などから火山ガスの特徴として次のようなことが考えられる。
二酸化硫黄の放出量は平成
12 年 9 月から 10 月には 1 日当たり 2 〜 5 万トンだったものが、最近数ヶ月は 1 万トンを超える日は少なく、長期的には低下している。そのような傾向にあっても数週間程度の期間や短時間では放出量が多いときや少ないときのゆらぎが見受けられる。二酸化硫黄の放出量の多い時、噴煙は火口壁に沿って勢いよく上昇しているが、最近の噴煙写真を見ると、放出量が少ないときは勢いがない傾向が見られる。噴煙の大部分は水蒸気であり、その一定の割合で二酸化硫黄が含まれていることが知られており、噴煙の状況から二酸化硫黄の放出量についてある程度の情報が得られるものと考えられる。
風がある程度強い時、二酸化硫黄は風下側に帯状に流される傾向にある。風上側では高濃度となることはほとんどない。また、山頂から青白い火山ガスの帯がたなびく状況が見られることがあり、このような時に、高濃度の二酸化硫黄が観測されることが多い。
北東部の火口縁の標高が低くなっているところから、青白い火山ガスが帯状にたなびくことがある。カルデラ内に一度溜まった火山ガスがあふれて流下するのか、たまたま弱い南西風のときに低い壁を越えて火山ガスが流れやすいのか現時点では不明である。
(1)
概況 三宅島では、一年を通して西寄りの風が吹くことが多いため東部に火山ガスが流下することが多く、この地域では高濃度の二酸化硫黄が観測され、その頻度も高くなっている。
しかし、東部でも、夏季は冬季に比べ高濃度の二酸化硫黄はあまり観測されない。西部では、東部に比べ全体的に低濃度ではあるが、夏季は冬季に比べ濃度が高い傾向が見られる。これは主に風向きが季節により異なるためと考えられる。
(2)
風向・風速と濃度上空の風の風下側で、風向の±
45 度の範囲(注)で高濃度となることが多い。風速が 7 〜 19 m/s 程度になると、高濃度の二酸化硫黄が多く観測されるようになる。一般に強い風が山を越えていく場合には、風下側では地表方向へ巻き込むような風が吹くことから、火山ガスも地表付近を流れ、山麓でも高濃度の火山ガスが観測されるものと考えられる。
なお、風上で高濃度の二酸化硫黄が観測されていると見られるデータもあり、地上風のデータを用いた評価も必要である。
注)風向の±
45 度の範囲とは、風向に対して真反対となる地点の± 45 度、例えば西風の場合、噴出口から見て、北東から南東にかけての 90 度の範囲内に入る地域をいう。
(3)
放出量と濃度二酸化硫黄放出量が低下するに従い、山麓で高濃度の二酸化硫黄が観測される頻度は減っている。しかし、濃度の最高値については、放出量の低下と比例して低くなっているとは限らない。放出量が多いときは噴煙といっしょに二酸化硫黄も勢いよく上昇していたと考えられるが、放出量が少ない今は上昇する勢いがないようである。従って風速によっては、二酸化硫黄があまり拡散せずに地表に降ろされ、帯状に狭い範囲に流れるので、時々高濃度の二酸化硫黄が観測されている可能性がある。
(4)
噴出口からの距離と濃度 山腹は山麓に比べて火口から近いため、高濃度の二酸化硫黄が観測されている。
山麓においても東部で比較的高濃度の二酸化硫黄が観測されている。その原因の一つとして、噴出口が火口の中でも南南東側に偏っており、東部がこの噴出口からの距離が近いことが考えられる。噴煙は噴出口に近い火口壁から火口の外へ出ていることが観測されているが、火山ガスについても同様であると思われ、二酸化硫黄濃度の高低は火山ガスが火口から外に出る場所からの距離によるのではないかと考えられる。
一方、噴出口から近いアカコッコ館観測点では、高濃度の二酸化硫黄が観測されていないなど、必ずしも噴出口からの距離に二酸化硫黄濃度が対応していない現象も見られる。アカコッコ館観測点上部の火口側に尾根地形があり、火山ガスは東西どちらかに分かれて流下し、アカコッコ館観測点は比較的低濃度であると考えられる。
このほかにも複雑な地形が山麓付近の濃度に影響を与えていると考えられる。
例えば、西よりの風の場合、風下に流されたガスが東部の深い窪地形(金層マール)に集まり、それが流れていくこともあり、三宅島空港観測点では、噴出口からの距離が近いことも重なって、特に高濃度の二酸化硫黄が観測されやすいと考えられる。
また、北東よりの風の場合は、南西部の谷地形に沿って吹き降ろす風になりやすく、南西方向に山腹から山麓にかけて火山ガスが流下しやすい状況になると考えられる。
(5)
降雨時の濃度 降雨時は、二酸化硫黄が高濃度となることは少ない。これは、降雨により二酸化硫黄が吸収されてしまうことによるものと考えられる。
なお、降雨時は、南または東よりの風が多いことから、高濃度となりやすい東部に火山ガスが流れにくい状況が生じていると考えられる。
(6)
高濃度になる時間帯高濃度の二酸化硫黄が観測されている三宅島空港観測点では、日中に比べ夜間の濃度が高くなっている。他の地域では明確な傾向は見えない。一般的に日中は海から陸地へ向かった風が吹きやすく夜間はその逆であるため、夜間に火山ガスが山麓まで流れやすい状態になるのではないかと推測される。しかし、そのような状態は山頂付近での風が弱い場合に出現するため、火山ガスは地表付近に流れにくく、もともと高濃度になりにくいことが示唆される。
(7)
濃度別の頻度分布の形態 都内の大気汚染常時監視測定局で観測されている濃度の頻度分布の形態は対数正規分布に近いのに比べて、島内で観測される二酸化硫黄濃度は、より高濃度に偏った分布となっており、対数正規分布とは明らかに異なった分布の形態を示している。
これは、単一の放出源である山頂火口から二酸化硫黄が放出され、風等の影響を強く受けて高濃度になることが多いためと考えられる。
(8)
短時間に高濃度となる状況島の東部では
5 分程度の短時間で見ても高濃度となる頻度が多い。ただし、その頻度は冬に多く、夏に少ないという季節変動も見受けられる。また、高濃度の二酸化硫黄が長時間継続して観測されることも多い。高濃度になるのは噴出口からの距離と地形の影響であり、季節変動は風向の変化によるものと考えられる。なお、 1 年以上観測が行われ、高濃度が継続することも多い三宅島空港観測点では、 5 ppm を超える二酸化硫黄の出現頻度や超過継続時間は減少傾向にあることが分かる。これは放出量の低下に伴う現象と考えられる。
(9)
高濃度の二酸化硫黄の現れ方二酸化硫黄濃度が低い状況でも濃度が高くなるときには、徐々に高くなるのではなく、急激に高くなることもある。
4 最終報告に向けて
三宅島の二酸化硫黄放出量は低下傾向にあるが、その終息時期を明確に示すことは難しい。
検討会は、このような状況の下、これまで観測した膨大なデータの収集・解析を行い、三宅島の地形や気象などと二酸化硫黄濃度との関係を中間報告としてまとめた。今後もデータは引き続き収集し、特に島の東部に高濃度をもたらしやすい西風の吹く
二酸化硫黄は、高濃度で曝露されると健康に影響を及ぼすが、ぜん息や心臓病などの疾患のある人には、低い濃度でも発作を引き起こすことや、長期間の曝露により、新たな呼吸器疾患を引き起こすことが知られている。
今後の検討会では、中間報告で得られた火山ガスの特性に加え、火山ガスと健康に関する国内外の知見を踏まえ、帰島後の健康被害を防ぐための安全確保対策などについて検討を進め、帰島のための判断材料を示す予定である。
