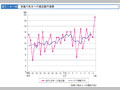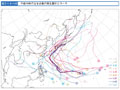4−4 風水害対策
(1)近年の風水害の特徴
平成16年の7月には,活発な梅雨前線により新潟県,福島県,福井県などにおいて豪雨となり,特に13日朝から昼過ぎにかけて,新潟県の長岡地域,三条地域を中心に,18日朝から昼前にかけて福井県で非常に激しい雨が降った。これらの豪雨により,人的被害として新潟県で15名,福島県で1名,福井県で5名の死者・行方不明者が出たほか,住家被害では,全半壊が新潟県で約5,400棟,福井県が約200棟,床上・床下浸水家屋が,新潟県で約8,300棟,福井県で約13,700棟となるなど,大きな被害が発生した。
また,平成16年の台風発生数は29個と平年をやや上回り,観測史上最多となる19個の台風が日本列島に接近し,そのうち10個が上陸した。これらの台風により,多数の人的被害や住家被害が発生した(図2−4−43 )。
特に平成16年10月20日から21日にかけて日本列島に上陸,通過した台風第23号は,暴風域が広く,また本州付近に停滞していた前線の活動が活発になったため,西日本から東北地方の広い範囲で暴風,大雨,高波となった。人的・住家被害は41都府県に及び,死者・行方不明者が98名,全半壊家屋が約8,700棟,床上・床下浸水が約55,400棟発生するなど全国各地で甚大な被害が発生した。
これらの平成16年の集中豪雨・台風等により,死者・行方不明者が236名,全半壊家屋が約17,500棟,床上・床下浸水が約165,800棟に及ぶなど,大きな被害が発生した。
b 水害の状況
我が国においては治山・治水事業の推進等により,水害による浸水面積(水害面積)は,昭和59年〜63年の平均が52,141haであるのに対し,平成11年〜15年の平均は26,398haと大幅に減少している(図2−4−44 )。しかしながら,河川氾濫区域内への資産の集中・増大に伴い,近年,浸水面積当たりの一般資産被害額(水害密度)が急増している(図2−4−45 )。平成16年は,集中豪雨や台風等により,全国各地で浸水などによる大きな被害が生じている。原因別に見ると,河川流域内の開発が進展することにより流域保水・遊水機能が低下し,洪水や土砂流出が増大するとともに,河川氾濫区域への都市化進展により被害対象が増加している。一方,都市河川,中小河川等の整備水準や下水道による浸水対策の水準は未だ低いこともあり,全体の水害被害額(一般資産等被害額)に占める内水の割合が大きい。
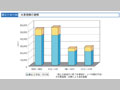
地すべり,土石流,がけ崩れといった土砂災害は,その原因となる土砂の移動が強大なエネルギーを持つとともに,突発的に発生することから,人的被害につながりやすく,また家屋等にも壊滅的な被害を与える場合が多い。
一般に土砂災害は,土砂移動の発生形態により大きく,地すべり,土石流,がけ崩れに分類される。火砕流を除外すると昭和60年〜平成16年の20年間の平均で毎年約920件の土砂災害が発生している( 図2−4−46 )。
発生件数の内訳は,がけ崩れが全体の約64%を占め,死者・行方不明者もがけ崩れによるものが最も多い。一方で地すべり・土石流は,がけ崩れに比べ発生件数は少ないが,阪神・淡路大震災に伴う西宮市での地すべり(34名),蒲原沢土石流災害(14名),出水市の土石流災害(21名),水俣市の土石流災害(15名)など,多数の死者・行方不明者が発生する災害があった。平成16年は,梅雨前線による集中豪雨,度重なる台風,新潟県中越地震,浅間山の中規模噴火などにより,新潟県,福井県,三重県,愛媛県をはじめとする全国各地で土砂災害が多発し,その件数は統計を開始した昭和57年以降最多の2,500件以上発生している。これらの土砂災害により,61名の死者が出ている。
近年の状況は, 表2−4−19 のとおりである。
平成11年には,9月24日に愛知県の豊橋市,豊川市内を襲った竜巻により,負傷者365名が発生し,また,10月28日には青森県で,強風と高波により入れ替え作業中の鉄道車輌が横転するなどの被害も発生している。平成16年は,6月27日に佐賀県佐賀市及び鳥栖市西部で発生した突風により,負傷者15名,全半壊家屋40棟などの被害が発生している。
また,平成16年に接近・上陸した台風は勢力が強く,台風第18号の接近・上陸に伴い,広島で最大瞬間風速60.2m/sを記録するなど,多くの観測点で最低気圧や最大瞬間風速,最大風速の記録が更新されており,住家被害や倒木,飛来物,屋根からの転落などによる死傷者が多数発生している。
高潮災害に対しては,海岸保全施設の整備や気象情報の精度向上等,積極的対策がなされてきたため,近年においては大きな被害は発生していなかった。
しかしながら,平成11年9月に熊本県で,台風第18号により12名の死者,平成16年8月の台風第16号は,一年を通して最も潮位が高い時期であったことから,瀬戸内地域の岡山県宇野港,香川県高松港などで記録的な潮位を観測し,3名の死者が出ている。昭和以降の主な高潮災害は 表2−4−20 のとおりである。
(2)風水害対策の概要
その後も集中豪雨の発生や台風の来襲が相次いだが,昨年の一連の集中豪雨や台風等による風水害では,避難の遅れや,特に高齢者の被害が相次いだことから,集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援が大きな課題となった。
災害時の避難勧告等の発令・伝達については,避難勧告等を適切なタイミングで適当な対象地域に発令できていないこと,住民への迅速・確実な伝達が難しいこと,避難勧告等が伝わっても住民が避難しないことが課題として挙げられた。
また,台風第18号の来襲時には20代の男性が暴風警報が出ている状況下において外出していて強風に飛ばされた看板にぶつかり重傷を負う例,台風第23号の来襲時には30代男性が大雨,洪水,暴風警報及び避難勧告の出ている状況下において外出していて水に流されて死亡する例がそれぞれ見られた。
これらには様々な要因が考えられるが,市町村としては,避難勧告等の意味合い(避難勧告と避難指示の区別等)が不明確であること,具体的な基準がないために判断ができないこと,災害の要因である自然現象や堤防等の施設の状況が十分に把握できていないこと,確実性のない段階での判断に限界があること等が要因として挙げられた。また,住民側からは,避難勧告等が伝わってもどのように行動していいかわからないこと,住民が自らの危険性を認識できないこと,切迫性のない段階での行動に限界があること等が挙げられた。
さらに,近年の特徴として,高齢者等の要援護者の被災が多いことが問題となっているとともに,避難途中に被災している人が多いのも事実である。要援護者の避難支援については,[1]防災関係部局と福祉関係部局等の連携が不十分であるなど,要援護者や避難支援者への情報伝達体制が十分に整備されていないこと,[2]要援護者情報の共有・活用が進んでおらず,また,プライバシー保護の観点から共有者が限定されており,発災時の活用が困難なこと,[3]要援護者の避難支援者が定められていないなど,避難行動支援計画・体制が具体化していないこと,の3つが大きな問題点として挙げられた。
このため,関係府省が連携して,避難勧告・指示,退避行動マニュアルの整備及び高齢者等災害時要援護者の避難支援ガイドラインの策定に速やかに着手することとし,有識者からなる検討会において検討を進め,平成17年3月28日に集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討報告をとりまとめ,同月30日の中央防災会議に報告された。
この検討報告では,「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」及び「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を示すとともに,国,都道府県,市町村等が避難対策を進めていくに当たっての方針をとりまとめている。
高齢者等の災害時要援護者の避難支援については,高齢者等の避難に時間がかかる方々が避難を開始するとともに,その他の方々は避難準備を開始することを求める「避難準備(要援護者避難)情報」を発令する必要性を打ち出し,市町村に「災害時要援護者支援班」を設けることにより,情報伝達体制の整備が必要であるとしている。
また,災害時要援護者情報を市町村,救助機関,避難支援者間等で共有するため,同意方式,手挙げ方式,共有情報方式の3つの方式を併用するとともに,平時からの情報共有を進めることが必要であるとしている。
さらに,一人ひとりの災害時要援護者に対して複数の避難支援者を定めるなど,具体的な避難支援計画(避難支援プラン)を策定することが重要であるとしている。
この検討会の検討結果については,地方公共団体等へ通知し,各種会議・研修を通じて浸透を図るとともに,市町村を中心とした避難勧告等の判断・マニュアルの作成や,災害時要援護者の避難支援プランの策定の取組みを関係府省が連携して支援していくこととしている。
COLUMN 災害時要援護者の避難支援〜情報共有の取組み〜 「集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会(座長:廣井修東京大学大学院教授)」の検討成果においては,現在,市町村等では以下の三つのパターンにより災害時要援護者情報の共有に取り組んでいることを紹介している。 例えば,愛知県豊田市は,介護保険の要介護3〜5の認定者のうち居宅介護の者,一人暮らし高齢者登録者等を対象に,要援護者本人又は家族から希望のあった者を登録するとともに(手上げ方式),一人暮らし高齢者に対しては民生・児童委員が戸別訪問を実施している(同意方式)。 また,神奈川県横須賀市は,個人情報保護条例に基づき個人情報保護審議会に諮問し,了承を得た上で,福祉関係部局が保有する一人暮らし高齢者,重度障害者,要介護認定者情報等を防災関係部局と共有している(共有情報方式)。 同報告では,避難支援プランを整備するため,市町村は,本人の同意を得て収集した情報を防災関係部局,福祉関係部局等で共有することを基本としながらも,早急な整備が不可能な場合や,同意が得られない要援護者への対策として,共有情報方式と併用することも必要であるとしている。 また,要援護者の理解を深め,避難支援プランの策定や避難支援者間での情報共有についての同意を得るためには,平時から接している社会福祉協議会,民生委員,介護保険制度関係者,障害者団体等の福祉関係者の協力が重要であり,さらに,要援護者本人から同意を得た避難支援者間で平時から情報共有しておくことも重要であるとしている。 |
b 平成16年の災害を受けての対応
安全で安心できる社会の形成を図るためには,昨年をはじめ近年の災害から浮かび上がった新たな課題に的確に対応すべく,これまでの災害対策を総点検し,その抜本的な改善を図る必要があり,国土交通省の社会資本整備審議会河川分科会に「豪雨災害対策総合政策委員会」が昨年11月に設けられた。検討すべき内容が多岐にわたるため,まず緊急に対応すべき事項について同年12月に「総合的な豪雨災害対策についての緊急提言」(以下,「緊急提言」という。)としてとりまとめられた。
緊急提言では,まず,昨年の一連の災害の特徴を自然的状況と社会的状況の変化の両面から分析し,今後の豪雨災害対策の基本的方向を示すとともに,河川・砂防・海岸の各行政機関が自ら行う情報提供,地域で実施する水防活動等に関する施策を中心に,早急に具体化を図るべき施策について提案されている。
緊急提言を受け,昨年12月に国土交通省において「豪雨災害対策緊急アクションプラン」が策定され,水防法の改正案を国会に提出するとともに平成17年度予算などに反映するなど現在,着々と関係する制度や体制の整備,必要な事業実施が図られてきている。
その後,同委員会は,防災施設等の計画・整備・管理のあり方や地域の防災力の向上についての審議を進め,今後の河川・砂防・海岸行政において取り組むべき施策等について検討を進め,平成17年4月に「総合的な豪雨災害対策の推進について」提言を得た。
また,集中豪雨,台風,大規模地震,中規模噴火等により,多発する土砂災害の実態を踏まえ,土砂災害による人的被害を軽減するため,平成16年12月に土砂災害対策検討会を設置し,総合的な土砂災害対策について平成17年3月に提言を得た。今後,この提言について,速やかに具体化を図り土砂災害対策を推進していくこととしている。
また,度重なる集中豪雨において,地方公共団体が管理主体となる中小河川の破堤の危険性が問題となったことから,国土交通省において堤防等の目視よる緊急点検を行うとともに,平成17年度からは,水害・土砂災害対策として必要な事業が流域単位で一体的・包括的に補助される制度を創設した。また,水防体制の強化や土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実を図る法改正を行うなど,総合的な水害・土砂災害対策の強化に乗り出している。
水害においては,特にハザードマップが有効で,洪水時等の影響範囲を示すことで,被害の予防や軽減に対する日頃の活動や備えの必要性を啓発できる。洪水ハザードマップについては,375市町村で作成が完了している(平成17年3月末現在)( 図2−4−49 )。
また,各地方自治体において,行政窓口での閲覧,配布,各戸への配布,公民館,病院等での閲覧,広報誌,ホームページ,電話帳への掲載,ハザードマップを使った避難訓練,小中学校の総合学習教材としての活用,配布にあたっての住民説明会の実施などにより,洪水ハザードマップの普及の取組みを行っている。